急増!燃え尽き症候群
燃え尽き症候群、別名バーンアウトシンドロームとも言います。
長引くコロナ禍が影響しているのか、最近ご相談件数が増えました。
医療従事者や介護職者、保育士などのエッセンシャルワーカだけでなく、
主婦(母親)からのご相談が急増しているのも気にかかるところです。

燃え尽き症候群とは…
これまで一生懸命に仕事に取り組んできた人が急に意欲を失って、
まるで燃え尽きたかのような状態に陥ることをいいます。
適切な対処を怠ると、うつ病をはじめとした精神疾患に移行することも
少なくありません。
燃え尽き症候群は、医療や介護のように“人”と向き合う職種に見られますが、
主婦(母親)のように、家事や子育ても“人”と向き合うという点では
同じかも知れません。
特に、コロナ禍で家で過ごす時間が増え、家事労働や養育の負担だけでなく、
家庭内での感染予防対策にもより一層の気を配らなくてはならないので、
身体的疲労や心のストレスは増すばかりです。

燃え尽き症候群の症状
“人”と向き合う職種は、仕事の成果を数値化することが難しく成果を実感
しにくいので、求められるままに際限なく頑張ってしまうことがあります。
その結果、心身が疲れ切ってしまい、あるとき突然、燃え尽き症候群になって
しまいます。
①情緒的消耗感
“人”と関わる仕事は相手との信頼関係を築くために、誠実さと思いやり
(優しさ)といった情緒的な関わりの積み重ねを求められます。
多くの情緒的エネルギーを注ぎ込むことで消耗した状態が続くと、
強い疲弊感を感じるようになり、仕事への意欲が一気に低下していきます。

②脱人格化
情緒的エネルギーが枯渇すると、それまでの人に対する思いやりや優しさの
ある対応ができなくなります。
この状態を「脱人格化」と言い、これ以上の情緒的エネルギーの消耗を
防ごうとする防衛反応だと考えられています。
急に冷たい態度で接したり、相手を無視するような態度をとるので、
周囲の人は「急にどうしちゃったの?」と違和感を感じることもあります。

③個人的達成感の低下
情緒的消耗感や脱人格化が進むと、当然のことながら仕事の質や
成果は低下します。
その結果、満足感や達成感が得られず、仕事に対する意欲や自信も
失ってしまうことになります。
離職や休職に追い込まれるケースも少なくありません。

燃え尽き症候群になりやすい人
①個人要因
真面目で責任感が強くひたむきに仕事と向き合い、人に役立つために
頑張り続けてしまう人ほど燃え尽き症候群になりやすい傾向があります。
また、年齢が若かったり、仕事の経験値が少ない人ほど、仕事に対する
理想が高い傾向にあり、理想と現実のギャップから発症リスクが高いと
考えられています。
さらに、理想主義(完璧主義)の傾向が強い人は、「こうあらねばならない」
というこだわりや思い込みが強いので、ときとして“やり過ぎ”てしまい、
燃え尽き症候群になりやすいと言われています。
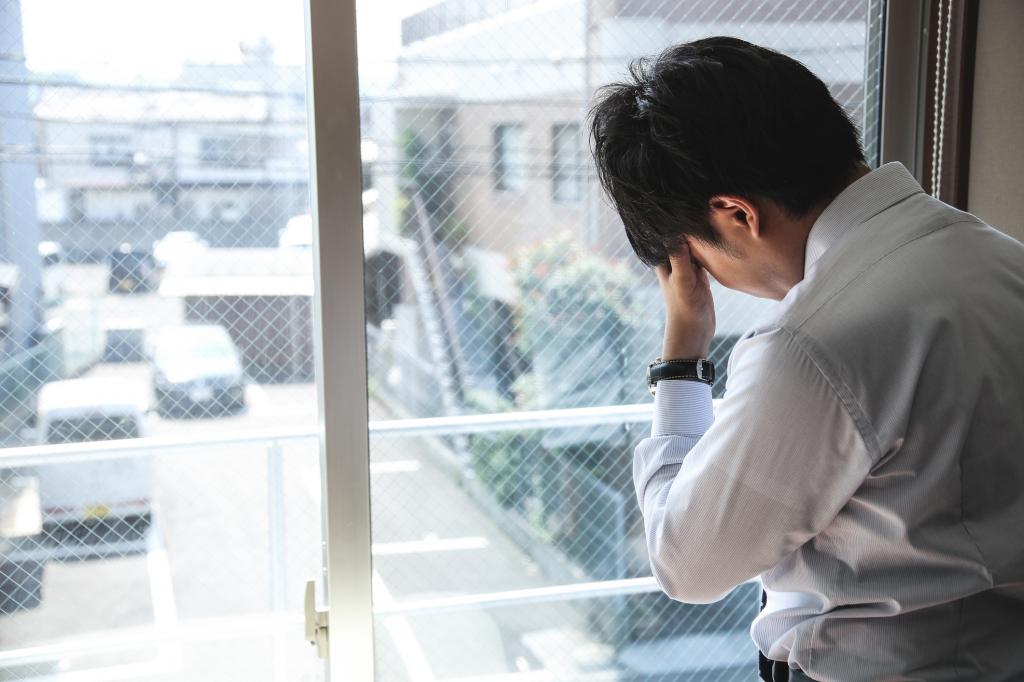
②環境要因
長時間勤務や休暇の不足、重労働による身体的負担、厳しいノルマなど、
働く場での過重負担が燃え尽き症候群の発症リスクをより高くしていると
考えられています。
また、仕事の内容と給料が見合っていないと感じると
「こんなに頑張っているのに…」という報われない感から仕事への意欲が
低下して発症する場合もあります。

『燃え尽き』を防ぐには…
燃え尽きる前に、自分自身の消耗度に気づくことがもっとも重要です。
①消耗度の数値化
燃え尽き症候群は、仕事の成果だけでなく消耗度(疲労度)も数値化
しにくいので、あえて数値化することで現状を客観視できます。
たとえば、今週の勤務時間、残業時間、休日数などを記録し、
勤務時間が○○時間以上になったら休みを取るというように、
あらかじめ休養をとる基準を決めておくことで燃え尽きを防ぐことができます。
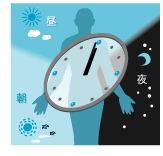
②心の消耗度も数値化
心の状態こそ数値化しにくいものですが、日々の感情を数値化して記録すると
客観的に捉えることができて、心のSOSに一早く気づくことができます。
たとえば、上司の一言にイライラした場合、ちょっとイラッとしたら1点、
我慢し難いほどの強いイライラ感なら5点というように数値化します。
同様に、苦しさ、悲しさ、ヤル気の無さなど様々な感情を数値化して、
1週間の合計が30点以上、または1日平均10点以上になったら気分転換を
図るなど、あらかじめ決めた基準を超えたらストレス解消のための
行動をすると心の健康が保てます。

③仕事だけを生きがいにしない
仕事の成果や他者に貢献したことで幸福感を得られるのは
とても素晴らしいことです。
しかし、自分自身の幸福感を他者に依存することにもなりかねないので
仕事だけに幸福感を求めるのはちょっと危険です。
日頃から仕事以外の楽しみを持つことは、燃え尽き症候群を予防するためにも
有効なことです。
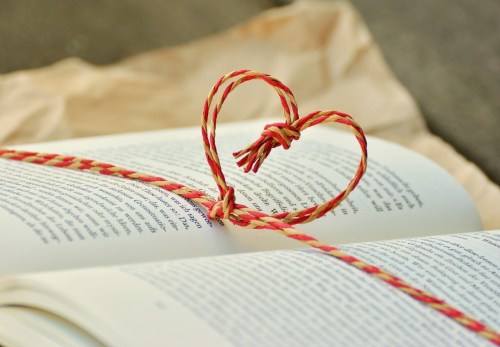
④理解と協力が不可欠
燃え尽き症候群の予防と対策は、個人的な取り組みだけでなく、
職場全体や周囲の人たちの理解と協力が必須です。
日頃からコミュニケーションを取り合い、気軽に相談できる関係作りと
遠慮なく休養できる仕組み作りこそが重要です。

◆当相談室では燃え尽き症候群に関するご相談にも応じております。
一人で抱え込まないで、まずはご相談ください。
ご不明な点はどんな些細なことでもお気軽にお問合せください。
